
コンサルタントの水道技術経営パートナーズが運営する、水道技術や経営の情報サイト「狸の水呑場」へようこそ。お問い合わせはこちらへ。
| 緩速ろ過法 | Slow Filtration |
緩速ろ過法とは,いうなれば浄水処理の原点とも言える手法で,除濁能力と生物処理能力の両方を兼ね備えている反面,大量の水を処理するには用地や維持管理,原水条件に制限がある,というのが一般的な見解です。生物処理能力に注目して,「生物浄化法」と呼ぶべきとの意見もありますが,一般に水道技術で生物処理というと生物接触酸化なので,ここでは緩速ろ過法として紹介します。
ただ,緩速ろ過方式は適切に導入し,適切な前処理をし,適切な運転条件で運転することができれば,他の処理方法よりも効果的な水処理方法として機能するようです。この「適切」が大変なのがネックといえばネックですが,緩速ろ過の利点,もっと見直されてもいいのでかもしれません。
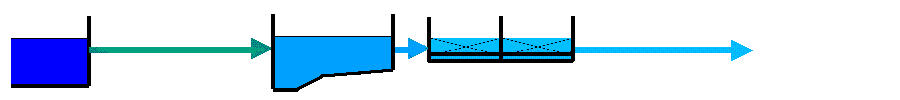
緩速ろ過といえば信州大の中本先生でしょう!ということで,先生のページをまず紹介しておきます。
- 地域水道支援センター
自然の仕組みを利用した緩速ろ過処理(緩速濾過)の話です。本当かなと懐疑的に見て!とは本人の弁。
【参考】
緩速ろ過法 Slow Filtration
1)施設構成
| 緩速ろ過法 | |
| 薬品注入設備 | − |
| 沈殿 | 普通沈殿池 |
| ろ過 | 緩速ろ過池 |
緩速ろ過池が中心です。これに,保安施設として普通沈殿池を前段に設けます。また,ろ過池の砂の洗浄用のヤードを要します。
さらに,緩速ろ過のメカニズムが解明されるに従い,緩速ろ過の根幹をなす生物相を制御するための具体的な前処理のアプローチについても除々に解明されてきているようです。この辺は前述の中本先生が詳しいわけですが,まだまだ,だれにでも狙った処理パフォーマンスを引き出せる,といった状況ではないようです。
2)理論
緩速ろ過システムは,緩速ろ過池の砂層の表層から水が浸透する際に,表層に薄い生物膜が自然発生的に生ずる現象を利用し,この層による懸濁質の補足と生物酸化作用による水質改善を期待するシステムです。
栄養塩類付着→藻類や微小動物→バクテリア繁茂→生物酸化→有機物や栄養塩の固定(固体化)→懸濁質の抑留→除去
さらに研究が進んだ結果,個別の生物相を適切にコントロールすることの意味についても除々に知見が蓄積されているそうです。メンテフリーを目指すとき,緩速ろ過は適切とはいえません。毎日現場に見に行かなければならないくらいが丁度いいとは中本先生の弁です。
また,緩速ろ過や生物処理が適切に運営されていれば,池内に生物相が生成するので,藻類が生えたり蚊を発生したりします。これらは,特に市街地の浄水場においては,また当時の衛生的環境の整備という社会的要請のもとでは,看過しえない欠点でした。このため,特に,緩速ろ過のメカニズムが十分に解明されていなかった時期には,殺藻やスカム流出防止などの処置が施され,これが緩速ろ過の処理性を低下させたということもあったとのことです。
3)除去対象
ろ過による漉し取り効果で懸濁質が,生物による酸化効果で有機物が除去できます。前者により懸濁質や細菌の除去が,後者により,アンモニア性窒素,臭気,鉄,マンガン,陰イオン界面活性剤,フェノールなども除去が期待できるとされています。
原水の性状に応じて,粗ろ過,酸素付与等の方法を適切に使用し,緩速ろ過池内の生物相を適切にコントロールすることができれば,緩速ろ過は大変優れたパフォーマンスを発揮します。ただし,例えば原水の滞留があるか,栄養塩がどの程度か,気温,流入濁度,溶存イオン等の様々な原水性状に適切な制御が必要となる。つまり,緩速ろ過の性能を引き出すには,それなりの技術力が必要,です。
4)導入条件
濁度10度以下。その他,BOD 2mg/L 以下,アンモニア性窒素0.1 mg/L,大腸菌群1000 CFU/100 mL,などの条件を目安に導入を判断するものとされています。汚染の進んだ原水,たとえば高pH,DO少,有害金属,シアン,残留塩素含有水は不適です。また,フミン質(色度の主成分)は除去困難です。
また,処理設備の面から見ると,生物相の制御のためには,以下のような点に注意が必要とのことです。
- 原水の滞留(ダムなど)の有無に応じてろ過速度や負荷量を適正化する
- 適切な前処理を導入する
- 臭気を発しない藻類(初期にはえる藻類,滞留させると藻類の相が遷移し,カビ臭を発生するタイプなどのしめる割合が増加する)
- スカムをしっかり排出する。滞留したスカムは,腐敗したり,悪臭を生ずる型の藻類が繁殖したりする温床になる。
ろ過池は懸濁質を補足することによりじょじょに閉塞しますので,一定頻度で砂を掻きとり,洗浄しなければなりません。このとき,新たに生物膜が発生する間の時間(馴致期間)が必要ですので,施設能力は大きめにすることが必要です。
- スウェーデン ロボ浄水場 緩速ろ過池
過去には緩速ろ過方式であった浄水場が急速ろ過に切り替えられる事例がありました。これは,原水水質の悪化によってろ過池の閉塞頻度が上がるなどして必要な水量を得られなくなったり,能力の増強が必要になって同じ用地内での改造を行ったりしたためです。また,急速ろ過の方が自動化しやすいこともひとつの理由でしょう。
右の写真はスウェーデンのロボ浄水場の緩速ろ過池で,急速ろ過を掻けたあとに緩速ろ過をする,という形をとっています。現地の担当者はコストがかかるのでよくないとは言ってましたが,水質的にはなかなかよい方法かもしれません。
.jpg)
5)総括
総括すると,緩速ろ過法は,一般に小規模で安定した水源があること,原水は比較的性状が悪いこと,浄水場の維持力が確保できる(水質に詳しい担当者が確保できるか,そのような努力がなされる)場合などで有効です。
実際のところ,大規模な水道事業体が緩速ろ過を切りかえていった理由を聞いて回った範囲では,やはりこの水質変化への技術対応の困難を指摘する人が多かったような気がします。もっとも,急速ろ過など他の方法でも,水を扱える技術者がいなければ同じことではあるのですが...
弱点としては高濁など原水条件の急激な変化に弱い傾向がある,とされることが挙げられます。大規模な緩速ろ過システムをうまく活用できている例では,上流域に貯水池や調整池を設けたり,原水の水質が良好だったり,といった,濁度や水質変化の調整のシステムを併設している場合が多いそうで,ロンドンなどもこの例に該当するそうです。
生物の力を借りる場合,その生き物が巧くこちらの目的にあった行動をしてくれるような環境を作ってあげないといけないのが普通です。動物映画の撮影,競走馬の調教,ペットの教育,魚の養殖などと全く同じように,生物を利用する緩速ろ過も,微生物の機嫌を損ねないよう日々のお世話をしてやれれば,物理的,科学的な水処理などよりも優れたパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。
ただ、逆の視点として、緩速ろ過は運営者のモラルや意識に依存する処理法であることをよく考える必要がある、という別の識者のご指摘があります。具体的には、表面のろ層をあえて荒らしたり棒でつついて穴を開ければ、清掃をサボっていても水を出すことができてしまいます。もちろんこんなことをしてはろ過の効果がえられないわけですが、砂の維持に手間がかかることもあり、モラルが低く、理論的な理解のない人間が維持運営に関わっていると得てして起こることなんだそうで、途上国では緩速ろ過はおすすめしない、という意見のベースには、このへんがあるようでした。
6)愚痴
緩速ろ過の好きな人のごく一部に急速ろ過や膜ろ過など他の除濁処理を目の敵にする人がいるようで,私宛のメールでもそのような主張を開陳されたことが何回かあり,実のところ辟易しております。
狸としましては,それぞれの処理方法の長短,知見を飲み込んだ上で,結果として,その時代背景に応じて処理方法が選定されたと認識しておりまして,仕事でもないのに無責任に処理方法選定の経緯に口出しをするつもりもありませんし,その判断が現在の知見から見てどうこうなどと言うつもりもありません。よって,そのような見解を求めるメールをいただいても,ご期待に添えない可能性が高くなります。あらかじめご了承ください。
緩速ろ過施設 Slow Filtration Equipment
1)普通沈殿池
緩速ろ過システムでは,緩速ろ過池が除去能力のほぼすべてを担当しますので,ろ過池の運用を間違いなく行うことが必要です。このため,水位を保つための着水井や,大きな流芥物の流入や,砂などによる過剰な負荷を防ぐ普通沈殿池といった保安施設を設けるわけです。普通沈殿池については沈殿池のページを参考してください。
- 沈殿池/沈砂池
沈殿池,沈砂池の構造にはそう大きな違いはありません。
2)緩速ろ過池
砂の表面に自然発生する微生物の膜によって水中の懸濁質や易酸化性の溶解物が補足,分解されます。原水の条件にもよりますが,藻類なども繁殖します。
生物膜がないと,緩速ろ過池はその機能を発揮しません。汚れなどによって砂の透水性が下がると,「砂掻き」などと呼ばれる作業で表層部を掻き取り清掃します。生物膜が再度生成するまでには半日から2日程度かかりますので,この間はろ過した水を供給せずに捨て水とします。たまに,事情をご存知ない方が「汚いから掃除しろ」とか宣うのですが,このへんの事情を是非ご理解ください。なお,最近は砂掻きロボットなるものも開発されたとの噂...これは情報を持ってる方が教えてくださるとうれしいです。
- 砂掻きの様子
ある浄水場における緩速ろ過池の砂掻きの様子。熟練工により,表層1cm程度を薄くはぎ取り,これを後述する洗砂場に運びまして洗浄し,また池に戻すわけです。

- 宮古島上水道企業団 袖山浄水場
浄水場に関する詳しい情報は訪問記(リンク切れ)をどうぞ。緩速ろ過池の事例で,硬度除去後にこちらに導かれてきます。噴水は...えーと...忘れました。
.jpg)
.jpg)
- 大分県 N町 緩速ろ過池
左の写真は運用中の緩速ろ過池で,写真ではわかりにくですが,緑色の生物膜が生成しています。右側の写真は,年1回の砂の全面洗浄のために表層を剥ぎ取った池で,池の構造がよくわかります。通常時の砂掻きでははここまでの砂の取り替えは行いませんので念のため。


設計指針に記載される設計条件は,処理速度4〜5[m/日]。砂層厚70〜90[cm],有効径0.3〜0.45[mm],均等係数2以下,などとなっています。
- 緩速ろ過池の例
こちらはもう少し広い緩速ろ過池。能力は日量2万トン級です。原水が湖沼水なので水質自体は比較的安定していますが,逆にあまり濁度が高い場合には取水はできないらしいです。
3)砂洗浄設備
- 大分県 N町 ろ過砂ヤード
前述のように,緩速ろ過では,補足された濁度成分は主として人手によって薄く掻き取るように除去されます。こうして掻き取られた砂はまず一ヶ所に集められます。左は宮古のもの,右は大分のものです。
.jpg)

- 大分県 N町 砂洗浄器
集められた砂は,下のような装置を利用して洗浄し,再度利用されます。砂を洗浄する装置や道具は様々で一定の仕様などは知りませんが,現場での工夫で対応されているように思えます。


【参考】
緩速ろ過施設を見学した際の写真です。ご案内ありがとうございました。
目次
緩速ろ過法
微生物による水質浄化と除濁を測る浄水システム。
緩速ろ過施設
実際の緩速ろ過施設の例。
備考・出典
設計指針(リンク切れ)より。試験勉強用にまとめたメモから起こしました。なつかしひ。
あと,中本先生の講演をいただいた分について修正しました。
更新履歴
- 120815 新様式で作成。
- 120610 運営について少しメモを追加。
- 080427 地域水道支援センターリンク修正。
| WaterPartnersJP all rights reserved | >>index >Top |