
| 防疫 | Sanitation |
病原性という脅威への対処は,水道の非常に大きな役割の一つです。水道システムの発明が巨大都市を可能にしたといっても全く過言ではありません。ここでは,防疫に関する基本的ノウハウを整理します。
防疫に関する基本知識
「防疫」とは,病原体等が水道水を通じて拡散することを防ぐことです。水道が当初導入されたのは,水系伝染病であるコレラやチフスの蔓延を防止することが主たる目的でした。
(1)疫学的脅威の種類
病原性生物には大きく分けて,細菌(Coli),ウイルス(Virus),原虫類(Protozoa)があります。WHOでは疫学的脅威を4種類に分類しています。
- 病原性細菌
コレラやチフスなど,過去に人類に甚大な被害をもたらしてきた病原性の細菌類です。現在では日本では深刻な脅威ではなくなりましたが,これは,水道が塩素されているためです。
- ウィルスなど小さなもの
小さすぎて物理除去が難しいうえ,物体と生物の境目のようなモノなので,塩素などの消毒剤も効果は限定的です。いまのところ,水系感染をするウィルスに直接の死亡など非常に深刻な影響をもたらすものがあるようには聞いていませんが,発熱や下痢等の影響でも体力が弱っている人にとっては致命傷になりかねません
- 原生生物
物理的除去は可能であるが,消毒は効かないもの。クリプトやジアルジアなどが該当します。原生生物の種類が違っても症状はあまり変わらないので,症状から種類が判断することが難しい点が厄介なんだとか。
- 再増殖(Regrawth)するもの
消毒がなくなれば再増殖するもの。基本的にはColiのバリエーションです。日和見感染をするものがこれに相当します。
(日和見感染は,以前は宿主=感染者の免疫力が低下した場合などに症状がでてくる感染症を指していたが,最近では再定義されている。新しい定義の日和見感染菌とは,ホストを経由しなくても増殖もしくは存続することができる類のことで,環境中で減少せず,大量に接種されて免疫力のある人でも感染させてしまう可能性がある。一般の病原性細菌は宿主の体内でしか増殖できない)。
また,直接人類への大きな脅威にならなくとも,原虫等の餌になることによって疫学的リスクを増大させる場合があります。
(2)HACCP
新しい疫学的脅威に対処するために,HACCPシステムがあります。HACCPは,以下の流れにて構成されるシステムで,赤痢,クリプト,ウイルスなどと一種一種のリスクに個別対応するのではなく,混入防止,除去,殺菌などの手段を組み合わせてトータルでマネジメントを図るものです。
- 社会的影響を評価する。
- 原料から製品までを管理するプロセスを設定する。
- 各ポイントでチェックを入れる。
- 上記プロセスを適正に運用し,結果を情報公開する。
HACCPについて解説しているサイトは多数。詳しい情報は公的なものが丁寧なのでいいでしょう。
(3)疫学的脅威の検出
疫学的脅威が発生しているかどうかは,実はすぐにはわかりません。たとえば,水系ではありませんが,SARSの脅威について人類が認識したのは相当感染が拡散してからでした。
研究室等で検出する場合でも,対象となる疫学的脅威を検出するためには,その数や濃度を増やさないといけません。すなわち,必ず濃縮もしくは増殖のプロセスが必要なのです。各々の測定の方法は以下のとおりです。
-
原生生物
ろ過や遠心分離などにより濃縮して顕微鏡などで係数するのが最も基本的な方法です。 - 細菌
FU(Coloney Forming Unit)で計測します。培地の上に微生物を含む可能性のある試水を置き,最近の塊がいくつできるかを係数します。
- ウイルス
PFU(Plaque Forming Unit)で計測するのが一般的です。Plaqueとは,ウイルスが宿主細胞等を冒して殺してしまうことによって生ずる斑点のこと。つまり,試水を,宿主細胞がびっしり生えた培地に垂らし,宿主細胞がウィルスによって殺されて空く穴を計測するのです。
いずれの方法でも,そのまま人体に感染する可能性がある対象を扱う上,さらにそれを増殖しようというのですから,バイオハザードを防止するハイレベル(Pなんたらとかいって番号が付いてるやつ)の試験設備が必要です。
では,社会に広がった感染の原因を突き止めるにはどうすればよいのでしょうか。
たとえば,クリプトの流行状態を把握するためには,病院で下痢症状を起こした人を対象に,先ほどのしちめんどくさい試験をやらないといけないわけです。さらに,感染した人が発症する確率,実際に下痢を起こした人のうち病院に行く確率などを掛け合わせていくと,クリプトに感染しているかどうかや,クリプトが流行しているかどうかについては,実は非常に判断が難しいのだそうです。また,旅行などで頻繁に移動する人であればどこで感染したかのモニタリングもかなり難しいということで,感染検知のマーカーとして捉えられる人が限定される問題もあります。
この点については,道義的には問題はありますが,疫学的弱者の健康状況,小学校の休校率,下痢止めの薬の売れ行きなどをモニタリングしていると,流行が分かるケースがあるとのことです。
【備考】
土木学会環境工学会のワーキングの講演でお話いただいた国立感染症研究所規制動物部,遠藤卓郎部長のお話をベースに加筆しました。
病原性生物の種類
(1)病原性細菌
コレラ,赤痢などの法定伝染病の病原細菌のほか,細菌ではO-157などもこの範疇です。原始的な微生物で自己増殖能力を持つため,培地などで培養してコロニー(塊)の数をCFU=colony forming unitという単位で測ることができます。
一般の細菌などは非常に増殖が早く,例えばフロ水を一晩置いておくと細菌は1000倍に増えます。ただし,それぞれの細菌は,それぞれに増殖しやすい適した条件というものがあり,病原性細菌類は,一般に,環境中ではほとんどめだった増殖ができないのが普通です。
感染力はさまざまですが,感染力の強いもので,101〜102CFU程度で感染を引き起こすとされます。塩素消毒が有効で,一般細菌や大腸菌を指標として,これらが死滅する程度の塩素濃度で,感染力を持つ細菌は死滅するため,指標としてはこれらが用いられます。
微生物に関するサイトを紹介します。
- 暮らしと微生物,環境と微生物@【田口文章のホームページ】(リンク切れ、2011年9月11日御逝去されました)
北里大学の教授が運営されているページ。微生物に関する情報量は圧巻であります。 - 【生物学が嫌いなんて言わせない!!】(リンク切れ)
微生物や生物科学に関するページ。コロくんが案内してくれます。
「Terrorist Attack in Nov.」により水道が微生物テロの対象となる可能性が現実のものになってしまいました。これまでの病原性対策が非作為的に発生することを想定したものである以上,これまでの対策だけでは十分でなくなった現実を直視する必要が強く認識されるところです。関連情報については災害のカテゴリーで扱います。
- 戦争・テロ
戦争やテロによる水道被害と対策について。微生物テロ関連もこちら。
【備考】
(2)ウイルス
ウイルスで有名なのはインフルエンザウイルスですが,これは水系伝播しないとみられています。水系では,A型肝炎ウイルスやロタウイルスなどが経口接触で罹患を引き起こす可能性があります。ただし,ウイルスは自己増殖能力を持たず,大腸菌などの細菌に自分のDNAを送り込んで増殖させます。よって,ウイルスを計数するためには,培地に一面に細菌を生やし,これにウイルス(のあると見られる供試体)を与えて,細菌の死滅によってできる穴=プラークの数を測ります。よって,ウイルスは,PFU=Plaque forming unitという単位であらわします。
腸管系ウイルスのリストを以下に示します。(参考文献より)
| ウイルス | 歯又は 亜型の数 |
惹起される疾病例 |
| エンテロウイルス | ||
| ポリオウイルス | 3 | 筋麻痺,無菌性髄膜炎,熱性挿間 |
| エコーウイルス | 34 | 無菌性髄膜炎,呼吸疾患,皮疹,下痢,流行性筋肉痛,心膜炎,心筋炎 |
| コクサッキーウイルスA | 24 | 水疱性口狭炎,呼吸疾患,無菌性髄膜炎,急性リンパ結節性咽頭炎,心膜炎,心筋炎 |
| コクサッキーウイルスB | 6 | 心筋炎,先天性心異常発疹,心膜炎,無菌性髄膜炎,呼吸疾患,胸膜痛 |
| 新しいエンテロウイルス | 4 | 無菌性髄膜炎,脳炎,呼吸疾患,急性出血性結膜炎,心膜炎,心筋炎 |
| A型肝炎ウイルス | 1 | 伝染性肝炎 |
| ロタウイルス | 4 | 乳幼児の急性胃腸炎 |
| レオウイルス | 3 | 起疾性不明 |
| アデノウイルス | 33 | 急性熱性咽頭炎,咽頭結膜炎,急性気道疾患,発疹性熱性疾患,肺炎,流行性角結膜炎 |
| バルボウイルス様因子 | ? | 急性胃腸炎,嘔吐,下痢 |
ウイルスの感染力は,A型肝炎ウイルスやロタウイルスで1〜101PFU程度程度とされ,一見細菌より強い感染力を持つように見えます。また,塩素への耐性は細菌より強いと考えられています。これは,主としてウイルスが非常に単純は構造とDNAを守る殻を持っているための考えられます。ただし,先ほど示したように,ウイルスの増殖のためには細菌など他の生物が必要なので,原水が清澄であれば伝播は防ぎやすいと考えられます。
水処理プロセスにおけるウイルスの除去率は以下のように提案されています。(備考欄資料より)
|
プロセス |
除去率(%) |
| 普通沈澱 | 0〜20 |
| 凝集沈澱 | 90〜99 |
| 活性炭吸着 | 10〜99 |
| 軟化(石灰) | 10〜70 |
| 軟化(過剰ソーダ灰) | 90〜>99.9 |
| 緩速砂ろ過 | 22〜96 |
| 急速砂ろ過(凝集沈澱を含む) | 98〜99.9 |
| 硅藻土ろ過 | 0〜20 |
| 活性汚泥法 | 75〜99 |
| 散水ろ床法 | 0〜85 |
| 酸化池 | 0〜96 |
| 塩素処理 | 90〜>100 |
各種ウイルスの詳細は,おのおのの名称を手がかりに検索サイトかなんかで調べてみてください。
【備考】
(3)病原性原虫
原虫には,クリプトスポリディウム,ジアルジア,アメーバ赤痢などがあります。また,これより大きい寄生虫,たとえば回虫やギニア虫など(興味のある人は目黒寄生虫館に行けば見れますよ...ただし中高校生くらいのカップルが山ほどいますが...)もこのカテゴリーに含めて考えていいでしょう。
これらは直接計れますが,前の3種類は環境中では種のような形(シスト)などの形態をとり,塩素耐性を示すために,水道水を媒介にして広がる危険性があることが分かってきました。
感染力は,シスト数で1〜101シスト程度と考えられています。最低1つから感染がありうるという見解です。
- 水系原虫感染症−原因生物と流行発生(リンク切れ)@【東京都健康安全研究センター】
水系原虫に関する詳しい知見が掲載されています。是非ごらんください。 - クリプトスポリディウム
病原性原虫,クリプトスポリディウムのページへ。 - ジアルジアの生態等について(リンク切れ)@【(公財)水道技術研究センター】
クリプトと並び,水道界でチェックされている原虫です。 - レジオネラ症防止指針(リンク切れ)@【大阪府臨床検査技師会】
むちゃ詳しいっす。ご参考まで。 - ミクロスポルジア
病原性原虫の一種らしい。詳しくはよくわかりませんが。 - 【目黒寄生虫館(MPM)へ行こうよ!!】(リンク切れ)
筆者も行ったことがありますが,寄生虫などを展示しているので非常に面白い。公式サイトではないようですが,紹介記事の充実度はぴかちゅうです。
1)レジオネラについて(レジオネラのページを分離するまで仮置)
水がたまるところで最近が繁殖できる環境では,細菌を餌にしてアメーバが増殖します。レジオネラはアメーバが存在しないと増殖できないそうですが,アメーバの体内で増えるのか,アメーバを補食しているのかはよく分かりません。
循環風呂の試験を行ったところ,塩素の供給を止める=細菌の増殖を許す=と,2時間後には細菌が増殖しはじめ24時間で一杯になり,3日目にはアメーバが発生,4〜5日でレジオネラが大発生するそうです。循環風呂ではヘアキャッチャ,生物処理槽が設けられているのですが,生物処理槽はレジオネラの培養槽のような役割を果たしているとのこと。ちゃんと管理のされていない循環風呂はレジオネラ症の点では非常にやばく,この辺のノウハウがビル管理法の改正につながったものと考えられます,
2)病原性原虫と光回復
生物は多かれ少なかれ破損したDNAを修復する能力を有しており,酵素の存在下で光回復と呼ばれるDNA修復,再活性化が無視まではできない,といったレベルではあるが発生する。高度な生物ほど実際に有効なDNAが少ないこと,修復能力を持つこと,などから,紫外線の影響を受けにくくなる。ちなみに,細菌等の自家蛍光という性質は,紫外線対策のために微生物等が獲得した能力ではないかとの説もあるそうです(紫外線のエネルギーを蛍光させることで緩和,遠藤先生講演より。)
ここで,気をつけなければならないのは,生残性と感染性との区別をはっきりする必要があるとのことです。
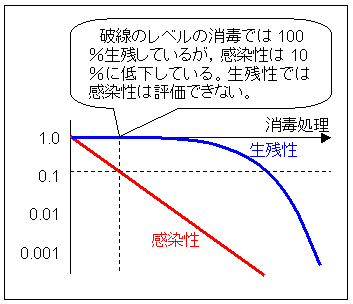 右図のように,生残性と感染性では相当感受性が異なるケースが多いそうでして,評価のスタンス,評価手法を明記していない疫学試験結果は意味が異なるとこと。クリプトなどの原虫の場合,感染性試験による評価が必須であるのだそうです。
右図のように,生残性と感染性では相当感受性が異なるケースが多いそうでして,評価のスタンス,評価手法を明記していない疫学試験結果は意味が異なるとこと。クリプトなどの原虫の場合,感染性試験による評価が必須であるのだそうです。
つまり,生き残っていても感染できない(生殖能力=感染能力が失われている)状態がありうるということでらしいです。
原虫全般については,効果があるという論文は直接照射したケースなど水の中に混入した原虫に適用できない,原理から見て原虫には有効ではないとの意見もありますが,クリプト対策としては光回復もないようだ,との見解が示されはじめ,この点に注目して,原虫対策としての導入が検討される事例が出てきているそうです。
【参考】
防疫の方法
(1)防疫に関する体制
水系伝染病の伝播を防ぐことが水道における防疫の目的です。そして,少なくとも当初は,水道の最大の目的でした。このあたりの経緯は、雑誌「水道」の連載シリーズ、「我が国の水道行政を検証する」に詳しいです。
防疫について所管しているのは厚生労働省で,そのうちでも国立感染症研究所や保険医療科学院(旧国立公衆衛生院)などが中心的なサーベイランス体制を敷いています。海外ではWHOやCDCが非常に有名で,WaterWeekやWater21などでもしょっちゅう出てきます。
- 【厚生労働省】
最新の情報を含め,官報には疾病関係の重要情報が掲載されます。 - 【保険医療科学院(旧国立公衆衛生院)】
水道界としてはこちらとのお付き合いが深いです。水道関係は国土技術政策総合研究所と国立環境研究所に移管されましたけど。 - 感染症疫学センター@【国立感染症研究所】
最新の感染症関係情報が手に入ります。 - 【CDC便り】(リンク切れ)
米国CDC(米国疾病管理予防センター)に勤務された方がCDCを日本語で紹介してくださっています。CDC関連のサイトもこちらからどうぞ。
【備考】
問い合せ対応を契機に作成。なお、「水道加入を義務付けられている」と書いてたのですが、下水道法と混同しておりましたので修正しました。
(2)水道を中心とした防疫対応
水道界としての対応を中心に据えた場合,防疫のためには以下の3段階の手順があるものと考えられます。
通常時の対処,というより予防の方法です。予防的段階では需要者の負担が小さくすみます。また,非常時であれば需要者の協力を得やすく,スムーズに取り組むことができます。水道では塩素消毒により防疫を実現しており,この手法もこのカテゴリーに相当するといえるでしょう。
このような対策には,水源保護や事故対策,消毒処理などが考えられます。
- 消毒
水処理のカテゴリー,消毒のページへジャンプします。塩素消毒,不連続点塩素処理などを掲載。
ワクチンのように,需要者の抵抗力を高めることにより,病原性の拡大を防ぐ方法があります。通常,水道の守備範囲とは考えられていませんが,公衆衛生上の観点からみれば,最終的にはもっとも効果を発揮する方法です。ただし,需要者の負担が大きく,本当に病気になってしまうリスクがあるため,特に危険な病原体以外には適用されません。
病原性原虫,細菌,ウイルスなどは,患者を媒体にして爆発的に増加することが最大の特徴です。ただ,特に深刻な病原性でもないかぎり,患者の隔離は人道上理解を得ることは難しいといえます。このため,患者の発生をすばやく知ることのできる情報ネットワークを構築し,患者の発生時に通常以上に防疫への注意を払うことは,非常に有効です。また,同時に危機管理手法についてマニュアル化したり,相当の訓練を積んでおくことが重要と考えます。
水系伝染病とは違いますが,雪印乳業における食中毒の伝播が大きな問題になりました。これは,「3)被害を把握する」ことに失敗した事例と言えるでしょう。クリプトなど,新しい病原性についても,そろそろ「当時の技術では把握できなかった」とは言えなくなってきておりますので,全面的に対応策を研究しておくことが,すべての水道に求められると考えます。
- カナダウォーカートンにおけるO-157禍@(リンク切れ)【Public Health Unit】(カナダ)(リンク切れ)
2000年度大騒ぎになったカナダでの水道媒介0-157の経緯。全部英語っす。 - 雪印乳業食中毒事件の原因究明調査結果について(中間報告)@【厚生労働省】
廃棄物最終処分場における硫化水素対策検討会報告書骨子。報道発表資料より。
病原性微生物や原虫など汚染が分かった場合の緊急の対応は,以下のような手順で行います。
- 感染症の検出
- 広報(煮沸,手洗の勧告)
- 緊急給水停止
- 浄水処理管理強化
- 汚染された施設の洗浄
- 復帰
また恒久的な対策例を以下に示します。これは,カナダのウォーカートンにおける,O-157汚染に対する抜本対策のリストです。
- 汚染された井戸の永久的な閉鎖
- 水源から蛇口までの全ての貯留及び配水システムの洗浄と消毒
- 操作方法及び監視設備の向上
- 行き止まり管やクロスコネクションの解消
- 本管の清掃及び取替
- 暫定的な膜処理設備の導入
- 汚泥の焼却
- 下水流出水の消毒処置
【備考】
目次
防疫に関する基本知識
防疫の対象と分類などについて解説。
防疫の方法
病原体の除去,抵抗力,被害等情報把握,の3点からとりまとめました。また,実際に汚染が起こった場合の対応についても併記。
備考・出典
- 2年近く放っておいたのですが,土木学会環境工学会のワーキングの講演でお話いただいた内容をベースに加筆しました。当日の講演のまとまりとレベルは,これまで参加した中でも最高クラスでした。でもこのページは重くなりすぎ。整理したいところです。
- 「上下水のウイルスと消毒」,「下水処理水中のウイルス」国際シンポジウム公演集 水中微生物研究会
- 「水中ウイルスの解説」昭和61年3月 日本水道協会
更新履歴
- 170615 リンク先変更。
- 121011 新様式で作成。
- 111122 HACCPとは@食品衛生のお話→HACCPとは@食の安全安心:リンク先修正
- 111122 暮らしと微生物:リンク先修正
- 010308 リンク追加
| WaterPartnersJP all rights reserved | >>index >Top |