
| 硬度 | Hardness |
各物質に関する情報をとりまとめたコーナーです。片っ端から集めた情報を載せる予定です。
水道への影響
1)水質基準項目
【水質基準項目】 300mg/L以下(カルシウム,マグネシウム等(硬度),味覚上の要件として)
硬水には明確な基準はありませんが,WHOの飲料水水質ガイドラインでは,CaCO3換算で,
- 60mg以下を軟水
- 60〜120mgを中程度軟水
- 120mg以上を硬水
と分類しています。硬度が”Hardness”の直訳とはびっくりでした...
ところで,硬度成分であるアルカリ土類金属の塩の形態によって,一時硬度(炭酸水素塩)と永久硬度(非炭酸塩),の2つの区分があります。各々の関係を示すと以下のようになります。
| 総硬度,全硬度 カルシウム硬度とマグネシウム硬度の和で示す。 |
一時硬度 炭酸水素塩なので煮沸によって分解沈殿する。 |
永久硬度 煮沸によって分解しない。 |
| カルシウム硬度 | Ca(HCO3)2 | CaSO4,CaCl2 |
| マグネシウム硬度 | Mg(HCO3)2 | MgSO4,MgCl2 |
一次硬度と永久硬度は,総硬度と総アルカリ度の間に以下のような関係があります。
- 総アルカリ度 ≧ 総硬度 の場合:一時硬度=総硬度,永久硬度=0
- 総アルカリ度 < 総硬度 の場合:一時硬度=総アルカリ度,永久硬度=総硬度−総アルカリ度
2)毒性や障害
極端な毒性はないようですが,軟水になれた人が硬度の高い水を飲んだ場合,下痢などを起こすことがあります。(筆者も山に行ったときよくお袋に言われました(^o^)...高原の岩清水っておいしそうですもんね。)このほか,生活用では,石鹸の泡立ちに影響する,薬缶や熱交換器のスケールがつく,などの障害があります。
3)汚染原因
国内では,沖縄のほか,山口県,四国などの一部では,石灰岩質の土壌が多く,ここで採取される地下水は硬度成分が溶け出しています。ただし,沖縄では渇水が頻繁に起こったことなどから,北部ヤンバル地域に水源ダムを建設し,ここで雨水が起源である表流水を貯留して南部に送水するようになってきており,これらの水源には硬度成分はあまり含まれません。
なお,海水淡水化によって得られる水では,塩分といっしょに硬度成分が除かれてしまうため,逆に硬度成分を加える,硬度の高い水とブレンドするなどの調整を行っていると思います。
4)処理方法
硬度処理方法についての簡易比較表です。ただし,この表だけで判断するのは適当でありませんので念のため。詳しい原水の条件をもとに,比較検討を行いましょう。
| 凝析沈殿法 | 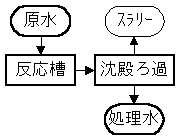 |
●原水が安定して高い硬度を有する場合に有利。 ●強酸,強アルカリを扱う。スラリー(沈殿)が発生するので排水処理が必要。 ●コストは比較的低い。維持管理者に知識が必要。 ●欧米での実績多い。 |
| イオン交換法 | 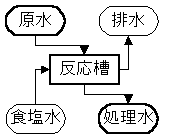 |
●中〜小規模に向く。 ●薬品の扱いが容易。 ●コストは高め。維持管理者にに知識が多少必要。 ●小規模施設の実績有り。 |
| 逆浸透法 | 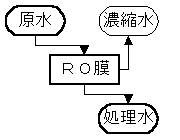 |
●小規模に向く。目標を高く設定できる。他の溶解性物質と合わせて処理可。 ●薬品の扱いが容易。ただし薬品洗浄操作の委託有り。 ●コストはかなり高め。維持管理は比較的容易。 ●小規模施設施設,工水などで実績あり。 |
| ペレット法 (詳細は後述) |
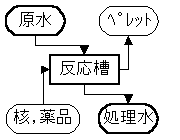 |
●中〜小規模施設に向く。凝析沈殿法を改良したもの。 ●強酸,強アルカリを扱う。ペレットを継続購入する必要あり。 ●コストは中位。ただし,成長したペレットは販売も可能な品質。 ●欧州で実績多い。日本での実績は比較的 |
5)検出方法
滴定法。緩衝試薬,呈色試薬を入れた原水に,ぽとぽとと反応試薬を落とし,その量で測ります。
特記事項
1)硬度の味への影響
硬度成分のことを「ミネラル」とよびます。ミネラルウォーターには硬度成分が水道水よりも多量に含まれます。ミネラルウォーターと水道水を同じ温度,塩素濃度でのみ比べると,大概の日本人は水道水の方がおいしいと感じるそうで,高すぎる硬度が味に与える影響が伺えます。ただし,硬度が低すぎてもおいしくありません。
- おいしい水
おいしい水の要件について。 - 水の賢い使い分け@【ためしてガッテン】(リンク切れ)
人気番組,試してガッテンのアーカイブ。
また,硬度が高いことが当たり前になっている地方(たとえば秋吉台の近く)などでは,ヤカンやなべにはぎっしりとスケールがついていても,「水はそういうもの」と思って使うそうで,ほとんど問題視しないといった話を聞きました。苦情の電話をかけてくるのは,他の地域から引っ越してきた人だそうです。もっとも工場などではボイラーにスケールがつくなど問題になるため,軟水化装置を各自つけなければならないそうです。
2)ペレット法
硬度処理を目的として開発された手法です。
- 宮古島上水道企業団 袖山浄水場
ペレット法の施設やペレットの雰囲気を見てみてもらうと...実機の写真を紹介します。1枚目は上屋,2枚目はタネペレットと生成ペレットの比較です。3枚目はペレットリアクタ本体,4枚目は生成ペレットからタネペレットを作成する工程のうち,最終工程である洗浄機です。5枚目は出荷を待つ生成ペレットです(^o^)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
このほか,詳しい情報は企業サイトにありますのでご参考まで。
- ペレットリアクター(リンク切れ)@【株式会社西原環境】
硬度除去装置の商品サイトについて。 - Ca(HCO3)2+NaOH → CaCO3↓+NaHCO3+H2O
【参考】
目次
水道への影響
基準,毒性や障害,汚染源,対処法,検出法について。水道としての視点からとりまとめました。
特記事項
当該物質に関連した情報について集めたものを掲載。
備考・出典
- ペレット法,硬度の分類などを追記。
- 昔行った検討書の資料など参考にしました。水道水質ハンドブック,上水試験法など。総硬度,一時硬度などについては西原環境衛生研究所作成の資料を参考にしました。
更新履歴
- 121003 新様式で作成。
| WaterPartnersJP all rights reserved | >>index >Top |