
コンサルタントの水道技術経営パートナーズが運営する、水道技術や経営の情報サイト「狸の水呑場」へようこそ。お問い合わせはこちらへ。
| 配水区のブロック化 | Block System |
配水区域のブロック化について。某市の計画時にいろいろ調べたのがベースになっています。ただ,その後実際の配水区設定などの経験を通じて少し修正したりしているので,必ずしも一般に言われるところの「ブロックシステム」の枠内に入っているとは限りませんが。
- 配水区の設定
配水区の配置方法について。
【参考】
配水ブロック化
1)ブロック化とは
ネタモトは厚生労働省かと思われますが,配水ブロックシステムの定義は以下のようになっているとのことでした。
| ブロックシステムとは、「ブロックをユニットとして、配水における運用・管理(情報収集・情報処理、施設操作)を行っていく機能を持つ施設形態ならびに管理形態であリ、配水管理の独立性、連帯性、単純性が確保されている階層システム」を指す。【第45回水道研究発表会要綱集より】 |
なお,ブロック化とは,既存の(あるいは新設の)配水管網にブロックシステムの特徴を与えることを言います。
2)ブロック化の目的
ブロック化の目的には,大きく分けて3つ(さらに細かく分けることもできますが)あります。
- 配水圧の適正化,均等化
- 水運用の高度化
- 工事,事故被害等の局所化
ブロックシステムの目的は,事業者がブロックシステムを導入することになった経緯と密接に関わっており,ブロック化にどのような効果を期待するのかで,ブロックシステムの形態が大きく異なる場合があります。
(1)配水圧の適正化,均等化
配水区内の地形の高低差がある程度以上ある場合,標高が低いところでは水圧が高くなり,また標高の高いところでは水圧が低くなります。この結果,配水圧の地域差が生じたり,水圧不足(150kPa以下),もしくは過剰(740kPa以上)になってしまう可能性があります。
ブロックシステムの導入により,配水区を標高差ごとに区分し,地形に応じた水圧を与えることでこのような水圧差を解消するのが,ブロックシステムの一つの目的です。
このような目的でブロック化を導入している事例としては仙台市が有名です。また,標高差が激しい事業の場合は,積極的にブロック化として進めていなくても,結果的にブロックシステムに近い配水システムになっていることが多く,幹線の整理などでブロック化を行うことが比較的容易なケースがあります。
(2)水運用の高度化
ブロックシステムの導入経緯が渇水などの場合,水運用の高度化がブロック化の大きな目的になります。配水区内の水需要を高精度に把握して適切な運用や漏水の把握を容易にするほか,複数の水源を融通してダムなど貯留可能な自己水源を温存するなどの使い方がされます。このような事例としては福岡市や北九州市のシステムが有名で,深夜には「このブロックで誰かがトイレに行った」なんてことまで把握できるそうです。
一つの理想は,配水区と供給点が1対1で存在し,区域内の水利用状況が把握できるシステムで,東京都ではこれに該当する配水システムが組まれています。もっとも,大ブロックで約20万人程度の給水人口はちょっとした大都市の水道と同じ規模ですが。
(3)工事,事故被害等の局所化
工事,事故被害の局所化は,計画的かつ局所的に配水の停止をできるようにすることで,計画的な管路の整備・更新に役立てるほか,地震時など大規模な被害が発生した際の復旧を速やかに行えるようにすることを目的とする導入を指します。
特に幹線については耐震化により極力被害を防ぎ,同時に断水ブロックの明確化によって末端の復旧を早めることがその基本的な考え方で,現在の配水管網整備の基礎的な考え方といえる概念でしょう。
新潟市では,新潟地震で大きな被害を受け,その教訓を生かしたブロック化が進められました。この取り組みは全国の水道事業者の注目を集め,ブロック化の嚆矢として注目されました。その中心的概念がこれにあたるものです。
3)ブロックの規模と決定方法
ブロック化は主として大,中,小の3階層から成り,大ブロックは水の融通を中心とした幹線システム,中ブロックは配水の制御を主目的とした中レベルの配水管網,小ブロックは断水や工事を想定した小区域で構成されます。このうちすべてがそろっていないければならないというわけではなく,目的に沿って必要と思われる機能を重視した整備が図られます。
ブロックの区分は,水理的条件(標高差,需用者数,大口需要者),施設条件(配水施設,応急給水設備,幹線,支線),管理条件(土地用途区分,町丁や小学校区,道路,線路や河川などの障害物)などを考慮して設定しますが,目安として,標高差で30m以内,人口で5,000〜10,000人(水量5,000m3程度),面積1km2程度以下,といったところでしょう。
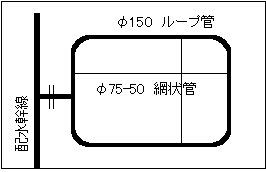
上図は中ブロックの基本的なイメージで,水理計算のページで推奨した形態です。上記条件でいくと,大体これくらいの規模か,もう少し大きい程度になるかなと思います。
【備考】
基本的にこのページは狸の見解です。特に数字についてはそのつもりで。ご意見をいただけるとうれしいです。
目次
配水ブロック化
配水区の配置方法について。
備考・出典
水道管路技術センター(現在のJWRC)の実施例など。
更新履歴
- 120817 新様式で作成。
| WaterPartnersJP all rights reserved | >>index >Top |